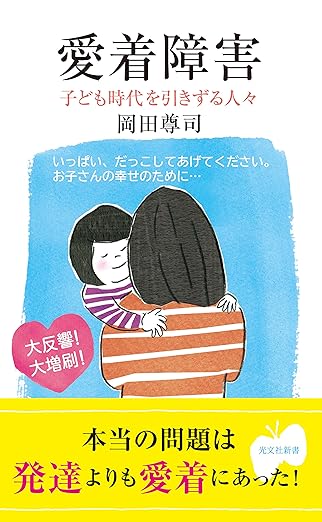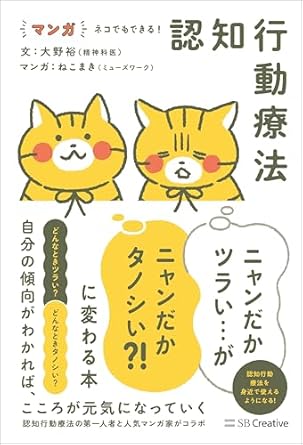世の中には様々な不登校支援があります。
公的で無料のものから民間で高額なものまで。
どの支援も下記にご紹介するどれかの理論を基にしています。
それぞれの考え方を知っておくことで自分に何が必要そうかがわかりますし、
自分でもある程度はできるようになります。
そこで不登校支援の基となる理論をたったの15分で理解できるようにご説明いたします。
楽しんで読んでいただけるように分かりやすさを重視しています。
ソリューションフォーカスト(解決志向)アプローチ
「子どもをほめましょう」とよく言われますよね?
これはこの理論から来ています。
子どもの良さに注目してほめる。
子どもの出来たことに注目する。
そして声がけにより自覚させる。
これをコンプリメントと言います。
大学受験で覚える必要がある単語で心理学ではよく出てきます。
なぜ褒めるのが大事なのか?
それは人間は自信があれば行動ができるから。
のび太君もドラえもんの道具があればジャイアンに立ち向かえます。
それは自信があるからですね。
とはいえ、現実には魔法の道具は無い。
ですが、認識次第で現実は変わります。
自分の良さを「認識」させることによって自信がある状態を作り出すわけですね。
認識というのはバカにならないもので、
最愛の人でも浮気しているのを知らなければ天国。
預金通帳に10億円があっても知らなければ不幸。
不登校の子も似たようなもので
これからの未来がある事に気づいていないわけです。
未来があるというのは10億円よりも価値があることでしょう。
あなたは15歳に転生できる権利があったとしたらいくらで買うでしょうか?
さて、良いところや出来たことは考えようによっては無限にあります。
ゲームに熱中できるとか、絵がうまいとか、
親に反抗する時はやたらと弁が立つとか。。。
そういったことを周りが気づいて本人に認識させていく。
そして本人が行動することによりさらに自信をつけていく。
それがソリューションフォーカスアプローチ。
そういうトレーニングはけっこうありますよね。
理論自体は簡単。
あとは身につけるだけです‼
愛着アプローチ
人間や哺乳類は「信頼できる人との安心できる関係」があると実力を発揮できると言われています。
また、傷ついた状況なども安心できる関係があると癒すことができると言われています。
それを安全基地と言います。
心の中のですね。
我々は家が無いと不安で生きていけないのです。
35年ローンのマイホームが跡形もなく消えていたらあなたも心が折れるでしょう。
もしくは終身雇用だと思っていた会社が倒産したら絶望するでしょう。あなたが45歳で。
物理的な家だけではなく心にもそれが言えて、
信頼できる人から絶対的に守られていると思えると実力が発揮できます。
「見捨てられない」と深い部分で確信していれば安心して生きていける。
それが評価次第では「見捨てられる」と心のどこかで思っていると生きづらいものとなってしまいます。
特に繊細な人は。
そもそも、世の中の人は結果しか見ません。
いくら頑張っても結果が悪ければ見向きもしないものです。
会社の社長がいくらがんばっても給料を払えなければ見捨てられてしまいます。
ぺこぺこしていた部下や仲良くしていた取引先も瞬時に去っていきます。
サッカー日本代表のFWがいくら努力しても試合で結果を出せなければ誹謗中傷の嵐。
さらに所属チームをクビになれば、社会の底辺からのスタートとなります。
チヤホヤされているスターでも一瞬で誰からも見向きもされない存在に。
みんな内心では不安で仕方がない。
世の中にはそうした絶望があふれています。
学校でも例外ではありません。
しかし、親くらいは何がどうあっても見捨てない存在であると。
それが「伝わると」子どもは勇気をもって前に踏み出すことができるのですね。
くわしく知りたいという方は精神科医の岡田尊司先生の本などがおすすめです。
また、よく誤解されがちなのが「愛情不足」という言葉。
傷つく親御さんが多くいますが愛情不足というケースは少ないでしょう。
ただ「適切に」愛情を伝えてきたかどうか。
もしくは「伝わっているかどうか」なんですね。
そのあたりもこちらの精神科医のさわ先生の動画を見ていただくとイメージはつかみやすいかもしれません。
課題の分離・共依存
不登校ではよく先回りや過干渉はよくないと言われます。
それは課題の分離という考え方からきています。
課題の分離とは子どもが自分の問題は自分の責任と認識して
問題解決能力を向上させること。
それにより自立できるわけです。
そもそも問題解決能力がなければ怖くて外に出れません。
なぜならば世の中は問題にあふれているから。
たとえば会社では、
上司とうまくいかない。
部下からつきあげをくらった。
取引先がわがままをいってくる。
電車が遅延して遅刻しそうだ。
などなどなど。
こういった問題を自分で解決できないといけないわけです。
*もちろん上司や同僚の力を適切に借りながら。
でないと、
会社に行くのが怖くなってしまいます。
学校でも様々な問題があります。
嫌いな友達がいる。
微妙な嫌がらせをしてくるやつがいる。
先生と気が合わない。
部活で試合に出れない。
部活の先輩がわがままなことを言ってくる。
などなどなど。
これらの問題から身を守れないと
生きていても単に傷つくだけ。
ボディーブローでもダメージが重なれば
ある日ダウンしてしまいます。
なので、不登校の子もなぜ学校に行けないのかがわからない。
それはささいな傷の積み重ねによるノックダウンが多いから。
さて、問題解決能力はどうすれば身につくのでしょうか?
どうすれば自分で自分を守れるのでしょうか?
それはトレーニングによってです。
算数の練習と同じですね。
ではトレーニングはどうすればできるのか?
自分でやるべきだと思えばトレーニングできます。
基本的に人間は自我があるので自分でやりたがります。
ゲームだって「プロゲーマーになりなさい」と
親が手取り足取り教えたら嫌いになるでしょう。
親や上司や先生が代わりに解決してしまうと解決のトレーニングができません。
子どもの反発をまねくだけ。
私を含めた大人はどうしても代わりに解決してあげたくなります。
しかし、そこを我慢して子どもに経験を積ませる。
失敗してもいい。
むしろ失敗に対して免疫ができたほうがいい。
目先の結果よりは経験や免疫が大事。
子どもにあえて失敗させて、
号泣させて暴れさせるべき時もあるのです。
他人の私などですらよく先回りして過干渉してしまいます。
親御さんは身内なのでおそらく過干渉をしてしまっている確率が高い。
お互い気をつけていきましょう。
ただし、ペース配分は大事です。
医師やカウンセラーなどの意見を参考にしましょう。
*共依存についても理解しておくと良いでしょう。
下記は精神科医のさわ先生の解説動画です。
約8分ですが倍速で見れば4分で見れます。
認知行動療法
認知行動療法は科学的な検証が一番なされており病院では保険適応されます。
筆者が対人恐怖症を克服したのも認知行動療法によるもの。
難しそうですが非常に簡単です。
認知行動療法は認知療法と行動療法が合体したものです。
行動療法はざっくり言うと大体のものは「慣れれば平気になる」というもの。
(乱暴な言い方ですがこのページではわかりやすさ重視で)
営業マンも最初は断られるのが怖いですが慣れると平気になります。
失恋も初恋での失恋は辛いものですが大人の失恋はそこまでではありません。
夫婦も知り合ったときは緊張したかもですが今では、、、
アメリカ人と話すのも最初は緊張しますが慣れれば平気。
サッカー選手のラモス瑠偉はブラジルから日本に来た時に
醤油や味噌や納豆のにおいが地獄だったそうです。
特に昔の外人からすると我々日本人はやばいものを食べているように見えるそう。
でも慣れればラモスさんもCMで日本食を美味しそうに食べるまでになりました。
対人恐怖症も慣れれば平気になりますし、
失敗も別に大したことはないと思えます。
もちろんペース配分は慎重に医師や専門家などの言うことを参考にしてください。
次に、認知療法ですが人は認知が変われば感情も変わります。
ダメージを受けにくくなるのです。
たとえば、大学受験の英語のテストで40点を取ったとしましょう。
これでは絶望してしまうかも。
しかし、実は合格最低点が50点だと知ったら?
「あと10点か」とやる気も出てくるのではないでしょうか?
事実は変わらなくても認知の変化により
感情が変わり現実が変わるわけです。
情報とその解釈によりですね。
親御さんも不登校でも成功したり一流大学に行く人がたくさんいると知ると
ほんの少し希望が湧いたりするでしょう。
それと同じです。
他の例も出しましょう。
お子さんが10万円の塾の夏期講習にいやいやながら行くとしましょう。
現代の若者は恵まれているのでいやいやかもしれません。
しかし、その10万円はお父さんが取引先に罵倒されながら苦労して稼いだものだと知ったら?
接待飲み会や接待ゴルフで楽しそうに見えても内心は家でのんびりしたかったとしたら?
(もちろん押し付けにならないようにうまくさりげなく伝えないといけません)
お子さんのやる気も変わるでしょう。
同じ10万円でも認知により大きな差が生じる。
同じ授業でも認知により大きな差が生じる。
そうした認知療法と行動療法を合体させたのが認知療法。
保険適応されるのも道理だと思いませんか?
よりくわしく知りたい方は精神科医の大野裕先生の本などをお読みくださいませ。
家族療法・構造派
家族療法の構造派も不登校支援でよく使われる理論です。
子どもが認知行動療法を受けてくれればいいのですがほとんどの子はいやがる。
なので、家族療法で間接的に子どもにアプローチすることが不可欠となります。
でないと、子どもを病院や面接室に連れてきてくださいと毎回お願いする羽目になるから。
構造派の考え方はシンプル。
1つ目は世代間境界
親は親。子どもは子どもと線引きをする。
でないと、混乱して様々な問題が起きてしまうのです。
会社でも上司と部下の線引きが曖昧だと大混乱です。
コンビニのバイトが店長に意見をしまくったら業務が成立しません。
銀行の社内でしょっちゅう下剋上が起きていては庶民もお金を預けられません。
半沢直樹はドラマの世界。
学校でも子どもが先生に土下座させていたら
民主的で実力主義的ではあるでしょうが問題でしょう。
語弊がある言い方かもしれませんが、
基本的には上の人に権力と権威を集中させたほうが問題が起こりにくい。
家庭であれば親です。
なぜならば、世の中には答えのない問題がたくさんあります。
しかし、決断して前に進まないといけません。
その時に最終的には親が決断をしなくてはいけないことはあります。
決断とは辛いものです。
しかし誰かが決断をしなければなりません。
これを下の人間に任せてはかわいそう。
そんな場面も多くあります。
くり返しになりますがペース配分などは慎重にやられてください。
できれば専門家のアドバイスを参考にしながら。
構造派の考え方の2つ目は夫婦連合
たとえば、部長と副部長が仲が悪いと部署は混乱します。
店長と副店長が犬猿の仲である職場とか地獄でしょう。
離職者が続出します。
コンビニの店長は「どんどん発注しろ」とバイトに言う。
副店長は「ロスをおさえるために発注をおさえろ」とバイトに言う。
これでは混乱するばかりでストレスも増大。
これと同じことは家庭でも言えます。
お父さんは「学校に行け」と言うが
お母さんは「ゆっくり休みなさい」と言う。
これでは悩みは深くなるばかり。
正しければ良いというものでも無い。
夫婦である程度は意見を一致させたほうが子どものストレスは減少します。
が、別に愛し合う必要までは無いのです。
連合というか同盟すればいいわけで。
不登校問題がある程度めどがつくまでで良いのかもしれません。
構造派の3つ目は父性と母性です
世の中には母性的な愛情と父性的な愛情があります。
どちらも大事なもので炭水化物とビタミンのようなもの。
しかし、母性と父性というのは矛盾します。
「どんなあなたも受け入れるわ」という母性的な愛情。
「ダメなものはダメだ」という父性的な愛情。
どちらも必要なのです。
社会でやっていくには。
現代社会では完全に母性的な組織というものは存在しません。
文化人類学の研究によると存在するのはジャングルの奥地だけ。
母性一辺倒で現代社会に適応するのは正直難しい。
トヨタやユニクロの社長が母性一辺倒であればあっという間に倒産です。
夫婦連合を作り母性的な愛情と父性的な愛情をバランスよく与える。
*片親の場合も工夫すれば両方を与えられます。
それが子どもの自立につながるのです。
ただし、タイミングとペースについては慎重な検討が重要。
医師や支援者にアドバイスを求めるほうが無難です。
疾病利得(しっぺいりとく)
疾病利得とは、病気や症状を持つことで本人が得ている心理的・社会的なメリットのこと。
例えば、病気によって「休める」「周囲から心配してもらえる」「嫌なことを避けられる」といった利益が得られる状態を指します。
私は元不登校なので言う資格が少しはあると思うのですが、
人間は弱いもの。
現状の不本意な状態に甘んじてしまう心理が誰にでもあります。
私が独立してかけ出しのころにこんなことがありました。
不登校支援だけでは食えずに道路の警備員としてバイトもしていた時のこと。
私は思ったものです。
「言われたとおりにやっているだけでお金がもらえるのか」
一方通行の入り口に立ち、たまに来る車に事情を説明するだけの仕事でした。
秋の過ごしやすい気候で立っているだけで幸せな気分。
責任も無いし、自分で考える必要もそんなに無い。
親や教師に反抗し自分の責任でやってきた私としては天国でした。
さらにはコンサルティング会社に入社し
若輩者ながらに経営者と議論をしてきた苦しい日々。
時には「早野さんは外してください」とか言われた日々。
その後に、私がやった警備員の仕事は
結果を出すとか出さないとかは関係ない世界。
心地よい湯船につかったような日々。
「もう頑張らなくていいんだ」と。
そんな時に古株のおじさんに言われたのです。
「ホームレスと警備員は抜けられなくなるから注意しろよ」と。
私のことを心底思って忠告してくれたのでしょう。
そんな人情味があふれる職場なのも魅力でした。
当時の私にとっては最高の修行の場でした。
人間は弱いもので誰もが現状に甘んじる傾向があります。
そんな時に「お前はこんなものじゃないだろ」と言ってあげる。
これも愛情だと思うのです。
ただし、「さぼりだろ」とか「お前はもっとできるだろ」と単純に言うのは考え物。
反発を招く可能性が高い。
また、傷つけるのも本意ではない。
医師や支援者の指導のもとで介入していくのが無難でしょう。
自己流でやる場合は慎重にやるのが良いです。
我慢して我慢するくらいがちょうどいいのですが
知っておいたほうが良い考え方かと。
自己受容
さて、これまでの理論も実行するには親御さんの心が安定しているほうが効率的。
心が乱れてはいてはどんな達人でもうまくいかないというもの。
心を安定させるにはどうしたらいいでしょうか?
それは自分が自分の安全基地になること。
自分に対して愛着理論を発動させるわけです。
大人も人間なので落ち込むことがあります。
失敗することがあります。
しかし、どんな時でも自分だけは自分の味方。
いかに世の中に批判されようと、
大事な人に罵倒されようと。
自分(親や支援者)だけは自分(親や支援者)を見捨てない。
誰が何と言おうと自分は自分の味方。
よく歌などで世界中が敵に回っても君を守るよみたいな歌詞がありますが、
あんな感じです。
ダメ人間であろうと、
欲まみれであろうと、
恥ずかしい人間であろうが、
犯罪者であろうが、
常に自分だけは自分の味方。
そういった状況ですと子どもに対しても落ち着いて対応できたりします。
なんせ安全基地にいるのですから。
さて、では自己受容を身につけるにはどうしたらいいのか?
お金を払って受講する方法もありますが、
ここでは無料の方法をご紹介します。
それはジャーナリングというものです。
グーグルも採用しているマインドフルネスの一種。
やり方は簡単で
思いついたものを紙に書きまくるだけ。
善悪とか意味があるとか無いとかを考えずに
紙に書きまくる。
(人に見られないようにしてください)
くわしい方法は下記の動画でご紹介しています。
何分間か書きまくるだけなんですが。
スキーマ療法
親御さんが子どもの言動に不安になったりするのは過去の経験や思い込みからきていたりします。
たとえば「安定した仕事につかないと価値が無い」とか
「常に努力して向上すべきだ」とか
「自分は愛されない人間だ」とか。
これをスキーマと言います。
カタカナ英語だとよくスキームと言いますね。
スキームとは枠組みのことで心理学だと心理的枠組みのこと。
「出来る会社員で出来る母親出ないと意味が無い」
みたいのがスキーマです。
これらは後天的に身についたもの。
たとえば、ジャングルの奥地の部族の人間は怠惰な生活を送っているそうです。
努力とは無縁な日々。
また、生まれつき自己否定する子どもというのもいません。
「不登校の子の母親で自分はダメな人間だ」というのも後天的なもの。
3歳児が自己否定するわけは無いので
どこかで後天的に習得したのです。
スキーマ療法に似たものにはインナーチャイルドとか潜在意識とか言われたりします。
とはいえ、そこまで深い部分に向き合う必要があるかというと人にもよるというところ。
知っておくだけで良いかもしれません。
能力の凸凹とトレーニング(発達)
近年、発達障害(神経発達症)とかグレーゾーンとかがよく言われます。
人間は誰にでも能力の凸凹があります。
しかし、あまりにも凸凹があると社会適応のさまたげになったりするのが世の常。
切れ者のビジネスマンも上司を殴ってしまっては社会に居場所がありません。
上司を殴らなくても部下を正論でつめてしまった結果、
自分の部下たちの離職率が飛びぬけて高ければ、、、
これもまた針のむしろに暮らすようなもの。
「オレはこんなに頑張っているのになぜ、、、」
うつにもなって休職してしまうのもわかるというもの。
さて、発達障害とかグレーゾーンとか診断されてもされなくても
不登校の子には大体凸凹があります。
なので、
「僕はこんなに頑張っているのになぜ」と傷ついていたりします。
そもそも凸凹は多くの人に共通してあるするので
誰もが長所を伸ばし短所は対策を考えるべきでしょう。
かといって、
「お前はコミュ力が無いからコミュニケーション研修を受けなさい」
では子どもは大反発します。
さりげなく、焦らずに研修をさせてあげる必要があります。
カウンセラーや医師にはなかなか会いたがらないので。
たとえば、お子さんにコミュ力が無いとしましょう。
その場合、家でホームパーティーを開く。
そして社交の手本を子どもに見せる。
さりげなくコツを教えてあげる。
(偉そうにならないよう)
粘り強く出来たところをほめる。
失敗しても見捨てない。
そうすると、
そのうちに足りないと思われた能力も伸びてきます。
また、計画性が無いと思えば
たとえば一緒に料理をするのが良いでしょう。
まず、買い物から子どもは計画性を学ぶでしょう。
(子どもにバイト代は出さざるをえないかもしれませんが)
料理でも段取りを学ぶでしょう。
それは勉強や仕事にもいきるはず。
筆者は不登校の時に料理で受験ノウハウを学びました。
レシピ(勉強法)を勉強して計画的にやれば目的地にたどりつくと確信。
その結果、自信を得てチャレンジに踏み出せたのです。
くりかえしになりますが、
カウンセリングとかトレーニングとかだと嫌がるので
遊びや日常生活の中にさりげなくトレーニングをまぎれこませるのが無難でしょう。
このあたりは専門家に相談するか、
親の会などで相談しながら進めるのが良いでしょう。
【重要】それぞれの考え方の対立と矛盾について
不登校というのは社会の中で起きているものです。
理科や数学と違い、社会の中で起きている問題には様々な矛盾が存在します。
それぞれの考え方には対立があるのです。
たとえば、貧困問題。
「平等にすべきだ」という考え方は社会主義とか共産主義と言われます。
良い思想ですが下手をすると北朝鮮とか中国みたいになってしまったりしてしまいます。
また、労働者がやる気をなくしてしまったりのデメリットも。
東大卒でも中卒でも同じ給料だと誰も勉強しないでしょう。
逆に「がんばった人が報われるべきだ」という考え方は資本主義(自由主義)と言われます。
これも非常に正しい思想です。
が、アメリカみたいにやりすぎると
「盲腸ですか?では300万円です」みたいな社会になってしまったりします。
自由すぎるだろと‼
また、億万長者もたくさんいるけど、
ホームレスもたくさんいて治安が悪いみたいな国に。
良い国というのは資本主義(自由主義)と社会主義(平等主義)でバランスをとっているもの。
どこかで妥協しているとも言えるでしょう。
日本や欧州などは資本主義をしながら、福祉などもある程度は充実しています。
少なくともアメリカよりは。
中国も共産主義をかかげながら資本主義的になり経済的に発展しました。
以前よりはマシだと答える国民が多いでしょう。
前置きが長くなりましたが、
不登校もこれと同じで各理論には矛盾があったりします。
というか、かなりあります。
矛盾があるのが人間社会というものだからです。
その間で各家庭なりのバランスの良いポイントを見出すことが重要。
ちょうどいいペース配分というのもあるでしょう。
たとえば、愛着理論と課題の分離や家族療法の構造派、疾病利得などは一見矛盾します。
どちらも正しい理論ですが「過ぎたるは及ばざるが如し」
ビタミンやミネラルも取りすぎるのは毒なのと同じ。
〇〇至上主義に陥らないことが大事だと思います。
偏差値至上主義や学歴至上主義が問題であるように、
学校復帰至上主義も問題だと思いますが、
学校「以外」至上主義も問題ですし、
心の安全基地至上主義も問題でしょう。
バランスの良い妥協点や取り組む順番を各家庭ごとで見出していただければと思います。
また、専門家の意見などを参考にされたほうが無難でしょう。
各ご家庭での妥協点の見出し方
NPOの効果的な活用の仕方
親の会の効果的な活用の仕方
(準備中)