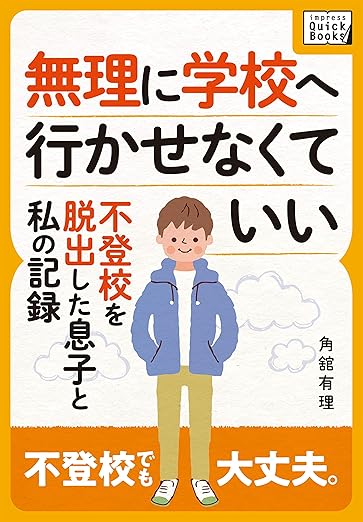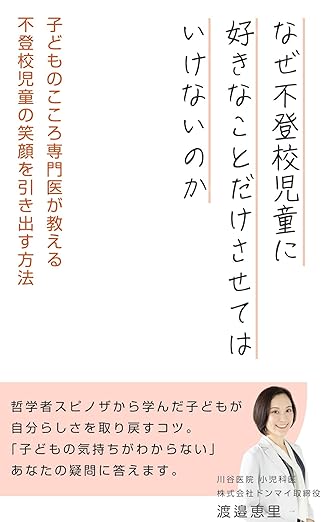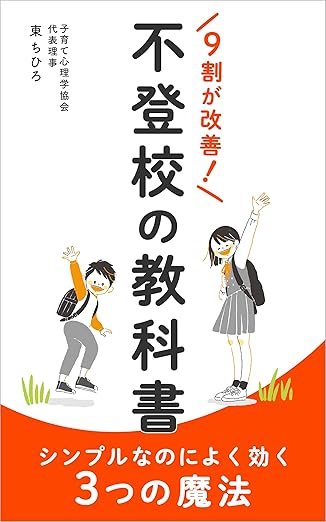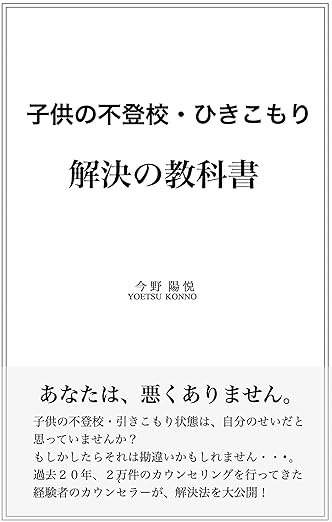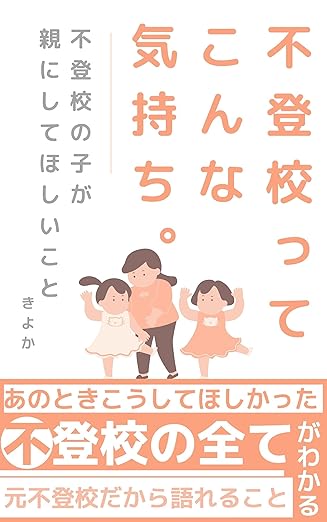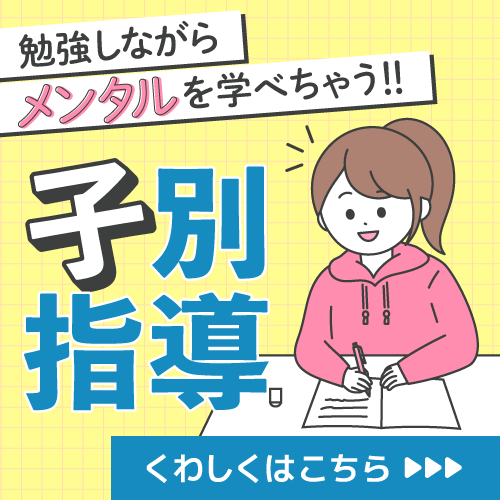不登校の本はたくさんあります。
それこそ山のようにあります。
「気になるけど読むのが大変そうで」
「でも気になる」
そんな方も多いのではないでしょうか。
この記事では不登校で「よく読まれている」本5冊分を要約してまとめました。
今回はシリーズ2回目になります。
15分程度で読めると思います。
不登校ではいろいろな矛盾することが言われます。
様々な本を頭の中にインプットしておくことでそれらの真意が理解できたりします。
お忙しい皆さんにサクッと不登校についてくわしくなっていただければと。
もちろん、よりくわしく読んでみたいという方は
ぜひ買って読まれてみてくださいね。
さて、「よく読まれている」の基準は1つはアマゾンのレビュー数です。
アマゾンレビューが50以上あればそれなりに読まれていると思われます。
注意点としては不登校に関する本はノウハウ部分とエピソード部分に分かれます。
ノウハウ部分は著者の主張ですね。
エピソード部分は著者の生い立ちだったり、不登校を乗り越えた経験であったり、
クライアントさんの事例だったりします。
この記事ではノウハウ部分に絞ってお伝えしております。
エピソード部分は感動するというか、
読者さまもモチベーションなどがあがるポイントなのですが、
残念ながらカットさせていただきました。
気になった本があればぜひ実際の本を読まれてみてくださいませ。
では、行ってみましょう。
この本に登場する息子さんは小5から中3まで不登校。
現在は大学進学を目指して通信制高校に在籍中。
(中3から適応指導教室に通学)
そのお母さんの記録が本書の主な内容です。
文体が素晴らしくお母さんの想いにふれないと伝わらない部分があり本書を読んでいただきたいところです。私も何度も目頭があつくなりました。
ここでは主にノウハウ部分というか心構え的な記述についてご紹介します。
お母さんが作られた「不登校の息子と向き合うために作った6つのマイルール」ですね。
その①押し付けないことを徹底する
味方だと思ってもらうために「学校」や「勉強」という言葉をしばらく禁句に。
部屋を片付けなさいなどの「〇〇しなさい」も言わない。
全てを受け入れて心の底から安心してもらい、少しづつ気持ちが外に向くようにして、
自然に社会に出られるように手助けをするという計画だったそうです。
(実際にそのようにされた記録が本書というわけで、実際に計画通りに進んだように見えます)
その②家庭を安心・安全なシェルターにする
「親は自分のことを理解しようとしてくれている」
「自分はここ(家庭)にいてもいいんだ」
と思ってもらえるような接し方を心掛けたそうです。
その③みんなと同じじゃなくてもいいと覚悟する
みんなと同じが正しいとは限らないという論理を腹落ちさせたそうです。
例として火事の時の群集心理でみんなが間違った出口に行ってしまうことをあげられています。
コロナの時もマスクのパニック買いなどがありましたが、
マスクなどはこのハイテク時代にいつまでも品不足なわけが無いんですよね。
(筆者補足)
多数派は間違いも多いという事例でした。
その④親がまずいろいろな価値観があると知る
世の中にはいろいろな仕事の仕方をしている人がたくさんいると知ること。
いろいろな進学の仕方をした人がたくさんいるということを知ること。
それにより息子さんの状態に対しても不安が薄らいだそうです。
これは誰でもすぐにできることですね。
その⑤子どもの個性を伸ばす手伝いをする
子どもの好きなことや得意なことを伸ばす手助けをすると。
例として料理をしたいので教えてほしいと言われたらレクチャーしてあげたことなどをあげられていました。(車の整備の本の購入などもあげられていました)
その⑥子どもを徹底して信じる
子どもが持っている成長欲や向上欲を信じることにしたとのこと。
赤ちゃんが勝手にハイハイしたり立ち上がったりするように生き物には自然に成長したいという欲求があるとのこと。
以上を心掛けて不登校期間を乗り切ったそうです。
良い口コミ
息子さん、著者がお母さんだから
しっかり自分の適性をみつめ、自分らしく生きる選択ができたんだろうなあと思いました。”人と同じでなくていい”
”やりたいことを駆け引きなく支援する”
”心の安全基地をしっかり確保する配慮をする”
”本音を語れる関係をつくる”著書の息子さんをみつめるまなざしがとてもやさしいです。
決してあきらめず、環境を整え、成長を見守る姿勢に頭が下がります。そんな著者の思いを肌でしっかりと感じていたんでしょうね。
息子さんが生きづらさをかかえながら
自分で考えて、生きていく術を身に着けていく姿に感動しました。不登校で悩んでいる方だけでなく、自己肯定感の低い方へもおすすめの本だと思います。
悪い口コミ
悪い口コミは特にありませんでした。
なぜ不登校児童に好きなことだけさせてはいけないのか 渡邊恵里著
精神科クリニックに勤務される医師である渡邊恵里さんによる著書です。
再登校、オンラインゲームから脱却することが重要という立場。
(フリースクールなども認める感じでもありますが)
不登校支援のために役立つ理論として哲学者スピノザによる「人が幸せに生きるための方法」が紹介されています。
スピノザによると人の行動は受動的な行動と能動的な行動に分かれます。
能動性とは自分がやりたい×自然と調和された行動のこと。
なので、1日中ゲームを続けるのは受動的な行動。
なぜならば周りと調和されてないから。
理性が働いていない。

夜中に音楽を大音量で聞くのも能動的な行動とは言えないそう。
ま~だいぶ迷惑ですよね。
能動的な行動(やりたい×周りと調和)を増やす方法として、
著者は次のことをあげています。
★意見を言いやすい環境をつくる
質問する時は2択か3択にする
(例)「カレーとラーメンどっちがいい?」
「ありがとう」「助かったよ」などの言葉をこまめに伝える。
★子どもにアドバイスを求められたら逆に質問して考えてもらう
(例)「あの子ならこんな時どうするかな?」
「前にやった時はどうしたかな?」などと質問する。
★葛藤に悩んで自分で解決するのを手助けする
葛藤とは「行きたい」と「行きたくない」のようなことです。
「ダイエットしたい」けど「食べたい」などもそうですね。
この葛藤を自分で解決できると周りと調和した行動がとれます。
つまり、スピノザの言う能動的な行動が増えるわけです。
上司を殴りたい。
でも殴るとクビになる。
なので「そうだ、飲み屋で同僚と愚痴を言おう」
そんな感じで多くの人は健全(?)な社会生活を営んでいるわけです。
子どももそうした葛藤を解決する力を身につける必要があります。
例えば、不登校の子が夜中に音楽を大音量で聞きたい。
でもそうすると親が眠れなくなる。
そこで「そうだ。防音壁を買ってもらおう」
となるとかなり平和的です。
さらに知恵を働かせて「ピアノ教室に行きたいから家でもピアノの練習をしたい」
とでも親に言えば子どものひきこもりに悩んでいる親も喜んで買ってくれるだろうとか考える。
相手のニーズも考えたうえで自分のニーズも満足させる。
葛藤に対して自分で解決策を考えられるようになればかなり健全です。
学校に行くと先生に怒られるかもしれないと思っている子どもの例があげられていました。
でも学校で友達と遊びたいと。
それならば、
そうだ、保健室なら行けそうだ、とか。
もしくは5時間目から行こう、とかで、
自分で解決策を出せると前に進んでいくとのこと。
こうした葛藤に親は寄り添うことが大事だと著者は主張しています。
結果よりも過程に目を向け、気持ちを聞いて、粘り強くそうした力を育てると。
★薬物療法
著者は医師なので薬物療法についても専門家。
どうしても受動的になってしまう場合は(周りと調和できない場合)
薬物療法も1つの手だと主張されています。
良い口コミ
不登校児童が学校に行く行かないではなく、児童の行きたい気持ちと行きたくない気持ちの葛藤を、十分に悩む事の大切さ解いています。
この葛藤は不登校児童ではない児童にも通ずる事があり、全ての事象に対して、親としてどうしたら良いか参考になると感じました。
悪い口コミ
能動的というのは当然わかるけど、そこに至るまでのやり方がざっくりすぎて、
私のようなアホにはよくわかりませんでした。そこがわかれば参考になると思うのですが。
*管理人も著者の言うことに全面的に賛成です。
しかし、子どもが「能動的に行動」するまではけっこう大変だなとは思っております。
実行するには著者の病院で支援をうけるのがベストだと思いますが、
難しい場合はスクールカウンセラーさんなどに支援を受けながら取り組むのが良いかなと思います。
著者はスクールカウンセラーさんで子育て心理学協会を主宰されている東ちひろさん。
元教員でもあります。
著者の主張は下記のとおり。
大事なことは子どもの自己肯定感ややる気と自信。
自己肯定感があれば学校でもフリースクールでも自然と行くようになる。
「ココロ貯金」を貯めることでやる気や自信がある状態になる。
そのためには以下の3つをやればOK。
②触れる。10歳までは抱きしめたり頭をなでたりしてスキンシップ。
10歳以降は一緒に遊んだり、一緒に何かを食べたりなどの共同作業。
③ほめるより認める。
(1)名前+あいさつ「〇〇君、おはよう」
(2)実況中継(目の前のことをそのまま言う)「よく寝たね」「汗をかいたね」
小さな変化を認めてもらった子どもはうれしくてさらに前進するとのこと。
存在が認められているということはうれしいですし、これはほめるよりも簡単なやり方ですね。

さらに親自身もココロ貯金をするとより子どものココロ貯金も貯まるというハッピースパイラルに。
お母さんどうしで話を聴きあったり、存在を認め合ったりするとなお良いとのこと。
ちなみにココロ貯金は怒られたり、説教されたり、さみしさを感じたりすると減るとのことです。
ですが、また貯めれば良いとおっしゃっています。
良い口コミ
まさに『教科書』でした!
お母さんは何をしたらよいか分からなくて、つらくて仕方ありません。
具体的に今日からできることが書かれていて、すぐに今から実践できます。
具体例の事例は、涙涙でした。
悪い口コミ
悪い口コミは特にありませんでした。
子供の不登校・ひきこもり 解決の教科書 今野陽悦著
著者は元不登校・ひきこもりで現在は不登校カウンセラーをしている今野陽悦さん。
今野さんは親が自分自身を自己受容をすることで不登校が解決すると主張しています。
自己受容とは「良い悪いの判断をすることなく、あるがままの自分をあるがままに認める」こと。
自分を肯定するとか好きになるとは違います。
「自分は悲しいんだなー」
とあるがままに認める。
「学校に行ってほしいなーと思っているなー」
と良い悪いの判断をせずに自分の気持ちを認める。
なぜ自己受容をすると不登校が解決するのか?
それは自己受容と他者受容が比例するから。
自分を受容できずに他者を受容することはできませんよね。
そもそも人は受容されてなんとか社会生活を送っていたりします。
会社で疲れ果てたサラリーマンもスナックのママに受容されて、
また会社に出社したりするわけです。
それが逆に、疲れ果てたサラリーマンも
スナックでも上司に「もっと頑張らないとクビだぞ」と説教され、
ママにも「もっとこうしたら?」とアドバイスされ、
帰宅後に家で奥さんにも「もっと早く帰って子育てを手伝うべきでしょ」
と正論を言われたら心が折れてしまうでしょう。

さて、不登校のお子さんも自己受容できずに苦しんでいるので、
親から受容されればお子さんも自己受容できて前に進めるわけです。
たとえば、お子さんが現実が思い通りにならないでひそかに苦しんでいるとしましょう。
そもそも悩む時は理想と現実があるからですね。
上でご紹介した渡邊恵里医師もおっしゃっていたことに似ています。
そんな時にお子さんが親に受容してもらったら?
たとえば「勉強しなくちゃな」と自分を責めているのを受容してもらう。
逆に「ぶっちゃけやりたくないな」と思っているのも受容してもらう。
その結果「今はいっか」と解決する場合もあれば、
「よしがんばろう」と解決する場合もあるでしょう。
人は受容されれば葛藤を手放せるという特徴があります。
会社の上司を殴ろうと思っても同僚に飲み屋で話を聴いてもらっているうちに「もういいや」となるわけです。
親が自己受容⇒子どもを受容⇒子ども自身が自己受容して葛藤を日々解決という流れになります。
*このあたりは管理人の補足なので今野先生のおっしゃっていることとは違う可能性があります。
また、自己受容することによって今すぐ親が幸せになり、子どもにも良い影響を与えることができるともおっしゃっています。

作中ではDoing、Having、Beingという言葉が出てきます。
Doingとは頑張る、勉強するなどの行動。
Havingとは報酬を得るなどの結果。
Beingとは〇〇になるということ。
(幸せになるとか)
普通はDoing⇒Having⇒Beingと進むかもしれません。
たとえば、勉強する⇒学歴を得て良い就職をする⇒幸せになる。
子どもが学校へ行く⇒安心できる⇒幸せになれる、とか。
しかし、この順番だと今が不幸ということになってしまいます。
今が不幸でも良い気がしますが、今が不幸だと不登校の子どもも親に寄りつきません。
子どもも「自分のせいで親が不幸だ」と思ってしまうのです。
そこで今野さんは下記のようにBeing⇒Doing⇒Havingと進めるべきだと主張しています。
(例)幸せな状態⇒勉強する⇒受験に合格する
(例)幸せな状態⇒子どもが学校に行く⇒不登校でなくなる、など
なぜBeingからスタートすると良いかと言うと、気楽にできてよりうまくいくから。
次のような例がわかりやすいかもしれません。
(例)幸せな状態⇒気楽に友達や異性と話す⇒友人や彼女ゲット
幸せな陽キャの人生ですね。
お子さんにはこうなっていただきたいもの。
(逆の例)あせって必死に婚活(Doing)⇒相手が逃げていく(Having)⇒不幸な状態(Being)⇒必死に婚活(Doing)⇒以下ループ
この逆の例と同じことを不登校の親御さんはやってしまっていたりします。
それも愛情からなのですが、子どもからすると重かったりもします。
必死に子どもを説得(Doing)⇒子どもが部屋にこもる(Having)⇒さらに不幸な状態(Being)⇒以下ループ⇒さらに子どもが部屋から出てこない⇒以下ループ
逆にこういうループが望ましいでしょう。
親が幸せな状態(Being)⇒子どもと話す(Doing)⇒まずは放課後でも先生と話してみるかという結果(Having)
*このあたりもかなり管理人の補足なので今野先生のおっしゃっていることとは違う可能性があります。
さてどうしたら今すぐ幸せな状態になれるのか?
それは自己受容をすると今すぐ幸せになれるそうです。
自分をあるがままに受け入れたら幸せな状態とのこと。
筋トレのようにトレーニングしていくのが大事とのことです。
*自己受容出来ていると今すぐ幸せが理解しにくいかもなので、管理人から補足。
①慶応大学の前野隆司教授が幸福について理系的な観点から研究していますが、その中に幸福の4要素というものがあります。
その中に自己受容が何回か出てきます。
つまり自己受容=幸福というのは科学的に証明されていることでもあるのです。
また、幸福度の高い人は生産性が30%高いという研究結果も出ています。(スウェーデンの研究)上記にあげた今すぐ幸せな状態で取り組んだほうが良い結果につながりやすいというのもある程度は実証されています。
②他にも様々な研究結果があります。
2022年の研究(Y Qianら)では、自己受容は精神的健康の予測因子として強く、20年にわたる追跡調査によると、自己受容が高いと死亡リスクが19%低く、寿命が約3年延びたという報告もあります。
また、女子大学生を対象にした研究では、「弱みを持つ自分を受け入れる」ことが主観的幸福感と強く関係していたとされています(大阪樟蔭女子大学の研究)
良い口コミ
子供の不登校がきっかけで読みました。
『自己受容』が問題解決への要だということは理解できました。
が、まだ「学校に行ってくれれば幸せ」が心の片隅に残っています。
そう簡単にはいかないと思いますが、『自己受容』を知っているのとそうでないのは大きな違いです。少しずつ進めていこうと思っています。
悪い口コミ
人生はそんな簡単ではありません。
偶然うまくいった方の本を読んでも参考にはなりませんでした。これが核心と思えるものがなくて残念です。
実際に親になってみないと分からないこともたくさんあると思います。
著者は元不登校で現在は大学生のキヨカさん。
キヨカさんは中1、中2でいじめられ、
中3のクラス替えで仲の良い友達がいなくなり、
担任教師とも相性が悪く、
父親の会社が倒産寸前で反抗期もあり父親とも衝突。
両親も不仲で喧嘩ばかり。
思春期の頃は壁に穴をあけ、家出を何度もしたそうです。
夜は仲間と遊びまわる非行タイプの一面も。
そんな感じで中3で不登校になったそうです。
心がぽきっと折れてしまったのだそう。
「そりゃ心が折れますわな」という感じですが、
それはキヨカさんが大学生であり聡明な方なので整理して書けるのだと思います。
渦中の子だとこうはいきません。
ほとんどの子は何も話さないからです。
(難しい内容なのでうまく話せない)
しかし、ありがたいことに当時の気持ちを大学生の今振り返って書いてくれています。
下記のような状態だったそう。
・なので、行きたくても行けなかった
・でもそのことをうまく伝えられずもどかしかった
(表面的には非行タイプ)
・学校のことを考えるだけで不安で心臓がばくばく
・親には申し訳なかった
・学校に行けなくて不甲斐ない
・とにかく居場所がない
・反抗的な態度はこころの居場所がないあらわれだった
・表面的には反抗していても自分を責めていた
・将来が不安で不安で仕方なかった
・親にはわかってほしかった
・消えたかった
・不登校中は楽しい時もあった
このあたりをふまえて、お子さんに向き合えるとお子さんの反応も違うかもしれませんね。
良い口コミ
息子の気持ちが理解できた気がします。学校に行きたくても動けず、こんなに苦しんでいるのかと思うと涙が出ました。
きよかさんの言葉のひとつひとつが、真っ直ぐで、とても心に響きました。繰り返して読みたいです。
きよかさんが仰るように、時間が経てば辛かった記憶も薄れていってしまうと思います。
でも不登校時代のリアルな正直な気持ちを書いてくださったことで、同じ悩みを抱えている子に、親に、大きな助けになっていくと思います。この本に出会えてよかったです。
悪い口コミ
悪い口コミは特にありませんでした。
以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。