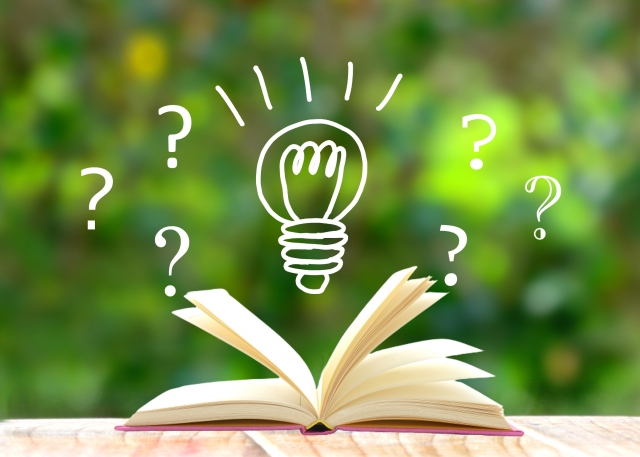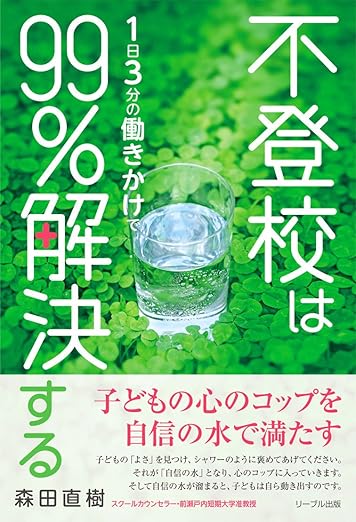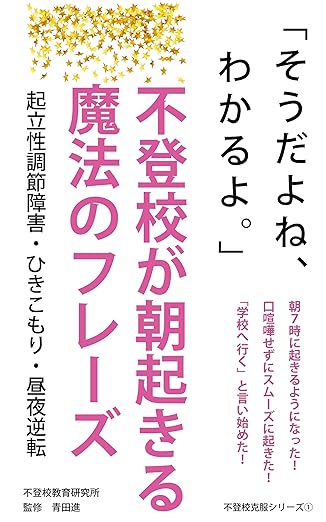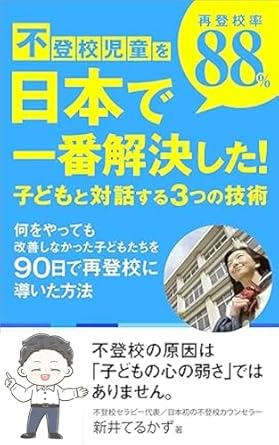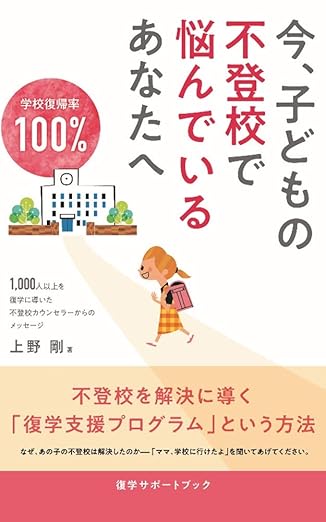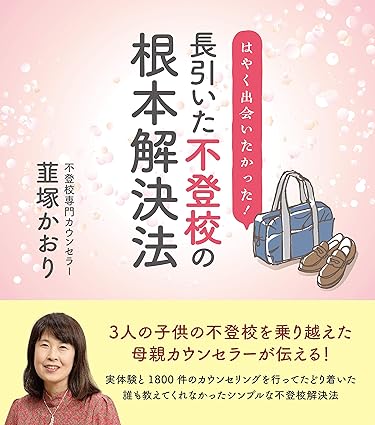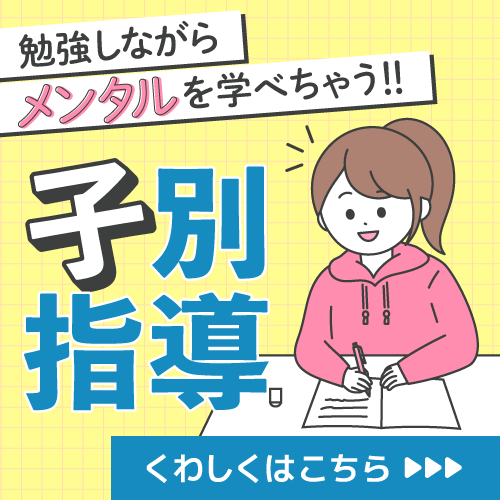不登校の本はたくさんあります。
それこそ山のようにあります。
「気になるけど読むのが大変そうで」
「でも気になる」
そんな方も多いのではないでしょうか。
この記事では不登校で「よく読まれている」本5冊分を要約してまとめました。
15分程度で読めると思います。
不登校ではいろいろなことが言われます。
様々な本を頭の中にインプットしておくことでそれらの真意が理解できたりします。
お忙しい皆さんにサクッと不登校についてくわしくなっていただければと。
もちろん、よりくわしく読んでみたいという方は
ぜひ買って読まれてみてくださいね。
さて、「よく読まれている」の基準は1つはアマゾンのレビュー数です。
アマゾンレビューが50以上あればそれなりに読まれていると思われます。
また、昔から読まれている本は時代を超えてと言うと大げさですが、
新しく出た本のお手本になっていたりしますので優先して取り上げています。
注意点としては不登校に関する本はノウハウ部分とエピソード部分に分かれます。
ノウハウパートは著者の主張ですね。
エピソードパートは著者の生い立ちだったり、不登校を乗り越えた経験であったり、
クライアントさんの事例だったりします。
この記事ではノウハウ部分に絞ってお伝えしております。
エピソード部分は感動するというか、
読者さまもモチベーションなどがあがるポイントなのですが、
残念ながらカットさせていただきました。
気になった本があればぜひ実際の本を読まれてみてくださいませ。
では、行ってみましょう。
*また今回は学校復帰派の本がたまたま多いのですが、
学校復帰派でなくても参考になる部分もいろいろとあるかと思います。
不登校は1日3分の働きかけで99%解決する 森田直樹著
元教員で元スクールカウンセラーによる再登校法です。
著者の主張は次の通り。
不登校の原因は子どもにストレスを乗り越えるための自信が不足していることにある。
そこで1日3回子どもをコンプリメント(承認と愛情を与えること)することで自信をつけてもらい登校に導くことができる。
コンプリメントは簡単なことではないがトレーニングをすれば誰でも身につけることができる。
*コンプリメントとは心理学でよく出てくる言葉で、
賞賛やほめ言葉のような意味。
著者は不登校の原因を「自信の水不足」と表現し、
コンプリメントにより「自信の水を与えてあげる」ことで再登校するとしています。
多くの親御さんは「本人が動くまで待ちましょう」と言われても困ってしまう場合も多いでしょう。しかし、コンプリメントトレーニングはいつからでも始めることができます。
具体的なやり方としては
①子どもの良さを見つけ親のうれしいという気持ちを入れる=自信の水
②子どもに伝える。
「世界一幸せなお母さんである」と自分に言い聞かせて下記のように言う。
(例)「洗濯物、たたんでくれて、お母さん、本当にうれしい。うれしいよ」と。
小学生であればだきしめるのも良いそう。
③一歩進んで「あなたには〇〇の能力があるね。すごいね」と伝えると、
子どもに自分の良さ、資源(リソース)を伝えることができるそう。
④毎日3つコンプリメントし、記録を取り振り返り改善する。

注意点は2つ。
*再登校後も続けることが重要。
*子どもが「何言ってんだよ」と言っても「本当にそう思うんだよ」と続けること。
電子機器に関しては著者は制限派ですが、
最近はスタンスも少し変わっているようです。
コンプリメントトレーニングに関しては解決志向アプローチ(ソリューションフォーカスアプローチ)と愛着理論に基づいて書かれているようです。
それらの理論に関してはこちらのページで解説しています。
良い口コミ
小学生の子供が不登校になり、あらゆる本を読みました。
この本を読んだ時、不登校は自信の水が足りないことが原因で、それを親が入れてあげるのだという内容を見て、これだ!と思い、すぐにトレーニングを受けました。
私の意識の変化や声かけで、これだけ子供の眼が輝くのかと感動しました。しばらくして再登校できました。
毎日の声かけは思っていたよりも難しいですが、森田先生の本を何度も読み直して、毎回気づきがあり、それをまた実践しています。
また、利他心が大切なことを学びました。
子供に伝えていきたいと思います。今もトレーニング継続中です。
何より親子関係が明るく良い関係になれたこと、これからの学校や社会での困難やストレスも、コンプリメントがあれば乗り越えられると希望を持てていることに感謝しています。
不登校でなくても、子育てで悩んでいる方に、ぜひ読んでいただきたい本です。
悪い口コミ
藁にもすがる思いで、こちらの本を読み、有料トレーニングも受けましたが、娘が自傷行為に出そうになり相談したところ、「マニュアルを読んでください。」というような、短い返事が来ただけであったことをきっかけに、中止しました。
不登校になっている子供を褒めて自信をつけさせることは良いと思いましたが、とにかく電子機器は禁止、ランニングは良いけど楽しめるスポーツはダメ、と、子供に理由を説明できないようなルールの強要をしたり、子供がどんなに辛そうでも、毎日学校は必要と洗脳したり、子供も親がどうしちゃったんだろうという気持ちになるだろうと思います。
娘はあの頃私を信頼できなくなってしまったと思います。何より大切なのは子供の命や健康だし、暴れたら警察呼べばいい、自傷するのは親がトレーニングの言いつけを守れてないからだ、って感じでビックリです。
娘はその後、ゆっくりと元気になり、私も変な洗脳されずに、ただ娘の心を大切に休ませ、今はとても元気になり学校に通っています。
トレーニングやめて本当に良かったです。
多分このトレーニングに一時的に登校しても、すごく子供が無理してる状態か、子供は親の本心がわからないままになるはず。
「そうだよね、わかるよ」不登校が朝起きる魔法のフレーズ 青田進監修
不登校界隈ではよく「規則正しい生活をさせることが大事」と言われたりします。
しかし、どのように朝起きてもらえばよいのでしょうか?
そう悩まれている親御さんも多いのではないでしょうか?
そんな悩みに対して書かれたのがこちらの本。
青山高校の元校長先生が監修。
「不登校をスムーズに朝起こす3ステップ」について解説しています。
著者によると
朝起きてこれずに昼夜逆転になってしまう心理には
「学校に行きたくても行けないストレス」
「親に申し訳ない気持ち」
「親からの登校プレッシャー」
があると言います。
なので、こうしたストレスを和らげる対応をお子さんにすれば
朝起きてくるとのことです。
ステップ①魔法のフレーズ(共感の会話法)
「そうだよね。わかるよ」と伝える。
(例1)
親「明日学校に行く?」
子「行かないよ」
親「そうだよね。わかるよ。行きたくないよね」
(例2)
親「明日学校に行く?」
子「無言、、、」
親「そうだよね。わかるよ。わからないよね」
*著者によると同情と共感は違うとのことです。
お子さんの意見に同意するのではなく理解することが共感。
「あなたとは意見は違うけど理解はできるわよ」と。
ステップ②共同作業法
共同作業法とは子どもと一緒に何かをすることで
「親は自分を認めてくれている」と思ってもらうことです。
作業自体はなんでもよく、アニメを一緒に見るとかゲームを一緒にするとか、
一緒に料理をするなどが例にあげられています。

ステップ③安心フレーズ
最後にこう言うそう。
「朝起きれても、休んでもいいからね」
著者のメソッドでは「規則正しい生活をする⇒学校復帰」というステップであり、
この段階では朝起きることを優先して良いそう。
ちなみに朝起きれたらお手伝いなどの午前中の用事を入れてあげると良いとのこと。
このやり方は愛着理論的ですね。
良い口コミ
朝起こす声かけ、休む休まないのバトル。
親子共々ストレスです。
時には腹立たしく思い、朝から子どもの様子に引きずられ落ち込みました。この本を読んで実行しました。
すっと自分から起きてくる回数が増えてきました。
それだけで、一筋の光です。
朝からスムーズに進むなんて、久しぶりで。。少しずつ子どもが良い方向に向かっていると、焦らず寄り添います。
悪い口コミ
ストレスや罪悪感が背景にあって学校に行けなくなっている子どもたちへの支援方法としては、とてもわかりやすく参考になると思います。
ただ、本当に体の不調によって朝起きられなくなっている子どもたちにとっては、この方法だけでは乗り切れない気がします。
例えば、慢性疲労症候群のように、医療の領域でもまだわかっていない病気があるので、そのことも視野に入れた支援のあり方についてもっと知りたいです。
著書によると不登校の原因は「愛着の傷」。
これまでもたびたび出てきた愛着理論ですが
人は幼少期に安心感が足りていないと言動が不安定になるという理論。
(かなりざっくりですが)
なので、不登校の子に対しては「安心感と承認を与えるような声がけ」をすることで
子どもは学校に行けるようになる。
そう著者は主張しています。
不安を与える声がけと安心感を与える声がけで下記の例をあげられています。
(例1)
A:「あなたが心配なのよ。そのせいであたしうつになりそうだわ」
B:「あなたは私の大切な子ども。だから早く元気になってね。お父さんお母さんが守ってあげるから」
(例2)
A:「朝ぐらい起きれないでどうするんだ。そんなんじゃ世の中でやっていけないぞ」
B:「大丈夫だよ。朝起きれなくてもなんとかなる。やっていけるよ」
(例3)
A:「テストで80点か。20点はなぜ間違えたか反省して対策しろよ」
B:「お、よくできたね。結果もいいしよく頑張ったね」
著者によると、不登校の親御さんはAのような声がけで育っていることが多く、
世代間連鎖により子どもが不登校になっていたりするとのこと。
*世代間連鎖とは価値観や習慣が親から子供に受け継がれること。
当たり前といえば当たり前ですね。
しかし、Bの声がけに変えることにより「安心感と承認」を得た子どもは
自信をもって動けるようになるとのことです。

良い口コミ
高校2年生の男の子の母親です。
無遅刻無欠席だった子が、突然学校に行かなくなり進級も危なかったのですが、この本に出会い、何とか進級できそうです!子供に対する私の対応を変えるだけでこんなにも効果があるのかとびっくりしました。
心療内科やカウンセリングなどに、子供を連れ出すのはとても大変ですし、実際に行っていません。
この本を読んで、私自身が実践しただけです。それで子供の方から自発的に学校に行くようになるなんて、夢の様な話ですが、この本を読めば、なぜなのかが理解できます!
なかなか、私自身も長年身に付いた言葉掛けや行動を変えきれない所もありますので、繰り返し読んでいます。
悪い口コミ
不登校へのアプローチとして愛着を採用されていることは共感します。ただ余りに単純化しすぎだな、と思います。
短い文章なのでしょうがないですが。愛着理論では捉えきれない事例や再構築が困難な事例もある一定数存在します。
それが筆者にとって12%ということだと思いますが、少なすぎる印象です。
内容についてはいいと思います。過半数の事例に適応できると思います。
今、子どもの不登校で悩んでいるあなたへ 上野剛著
復学支援機関エンカレッジの代表が書かれた本です。
これまでの3つの本とは違い家庭教育を重視しています。
家庭教育とは「親が過保護や過干渉をしないことで子どもの問題解決能力育成を助け、
自立を促す」という支援です。
子どもにしっかりとしたソーシャルスキルを身につけてもらおうというわけですね。
ソーシャルスキルにはストレス対応や嫌な人とのコミュニケーションなども含みます。
ちなみに家庭教育に関しては教育基本法第十条に「親が取り組む責任がある」と明記されています。
また、エンカレッジの支援では家族療法により家庭教育を進めていくという方針。
子どもの不登校の原因は「家族システムに問題があった」と認識する立場を取ります。
よくある家族システムとしては下記のようなものがあげられます。
母と子は母子密着で忙しい父親はかやの外。
なので、いつも母子VS父親という構図。
こうなると子どもは父親に叱られたりしてストレス耐性が育つべきであるところが、
ストレス耐性が育ちません。
さらには子どもが親と同等だと勘違いし、
わがまま放題になってしまったりします。
当然、外の世界では通用しないので、
ますます母親に甘えるか、やつ当たりするかとなってしまいます。
そこで家族構造を変えることや家族会議を行うこと、
さらにはソーシャルスキルを身につけさせる声がけなどで事態の打開をはかっていきます。
ソーシャルスキルトレーニングでは「問題所有の原則」を元に、
親が指示・命令や先回りをせずに子どもに自分で考えさせながら解決能力を育てていきます。
問題所有の原則とはその問題が「誰の問題」かということ。
たとえば、宿題をやるのは子どもの問題です。
宿題をせずに怒られるのは子どもなので。
このようにして子どもがソーシャルスキルを身につけ、
問題解決能力を持つことにより、
学校に行くのが怖くなくなるというわけです。
*明らかに子どもの問題でない時は親が介入する必要があります。
たとえば、地震で命の危険があるなど。
ただ、実際は子どもの課題か親の課題かの線引きは難しいところだと思います。
この本は上記の3つの本と違い家族療法の構造派や課題の分離の考え方を中心とした支援ですが、
非常に重要な考え方だと個人的には思います。
*家族療法や課題の分離に関してもこちらで解説しています。
現実にはどこでバランスを取るかが非常に難しいところですが、
難しい話をわかりやすく紹介されている良書だと思います。
それでもやはり書評などを見ると誤解されている部分はあるように思いますが。
また、愛着理論派などとの論争はたまに見かけます。
私見では結局は「時と場合による」というのが実際ところではないかと思います。

家族間のバランスに注目した手法
良い口コミ
この本の中で私が一番心に残った言葉が、「子育てではなく親育ち」です。
子どもの不登校の原因や解決には「子どもをどうにかしよう」じゃなくて、
親が家庭教育を学ぶことが大切だと教えられました。著者の復学支援機関にお願いすることで不登校が100%解決されるという所もありがたく素晴らしいことですが、一番は家庭内だけでも不登校解決の希望の光がある所です。
夫と「どこに頼めば息子の不登校は解決するのか」と常に支援機関に頼ろうとすることばかり考えていました。
しかしこの本と出会い、もう一度家庭内で息子と向き合い、そのために私たちが変わろうと思えました。
子どもとの正しい向き合い方も具体的に書かれています。
指示や提案を控える、親の価値観を押し付けない、叱り方についてなど。最初はどれも私たち夫婦が出来ていないことだらけだったので戸惑いもありました。それでも状況を変えたいの一心で今までの子育てと180度変えることにより、なんと子どもにも変化が現れました。
このまま不登校が続けば、直接著者の支援機関にお願いしようかと思っていましたが、本の内容だけでも復学出来ましたことをこの場を借りて感謝をお伝えできればと思います。本当にありがとうございます。
今まで出会った本の中で、私たち夫婦にとっては人生を変えた一番の本です。
悪い口コミ
私には合いませんでした。母親のせいと言われているような印象を受けた本です。 アマゾン書評より
この本を書かれたのは3人の子どもの不登校を乗り越えたという不登校専門カウンセラーの韮塚かおりさん。上の4つの本とは違い、より親御さんの内面にフォーカスした内容となっております。
これまでにご紹介した本は声かけやノウハウが中心でした。
しかし、韮塚さんはお母さんの内面こそがより重要であると主張されています。
(どちらが良いかはみなさんが個別にご検討されてください)
カウンセリングでも復学支援でも何をやってもうまくいかなかったという韮塚さん。
親が変われば子どもが変わるということで、
親が変わる3つのステージを提唱されています。
ステージ①子どもへの接し方や対応の仕方が変わる(外の言動)
子どもへの声がけの仕方などを変えるなど。
ステージ②親の意識や在り方が変わる(内面)
子どもをありのままに受け入れる。
親も自分自身を自己受容する。
親が精神的自立をする。
ステージ③親の無意識の不安が安心感に変わる(内面の深い部分)
インナーチャイルドなど心の深い部分が癒される。
インナーチャイルドとは子どもの頃の意識や感情を伴った記憶のこと。
ステージ③になると自然にステージ①や②のことができるそうです。
韮塚さんによると不登校の原因は親の生きづらい不安感。
たとえば、人にどう思われるか怖いとか本音を出せないなど。
「親の育てられ方」により親が幼少期に傷ついた心の深い部分が不登校の原因。
(世代間連鎖)
なので、そこを癒せば問題は解決するというのが著者の主張です。
アマゾンレビューでも賛否両論ありますが、
合う方には非常に合う力作だと思います。

良い口コミ
作者の辿ってきた道が、今の私と同じだどいうところに驚きました。
まわりは、どんどん解決していってるのに、自分だけ取り残されているような感じに思っていました。
そして、辿り着いた根本的な原因に、今、私も気付くことが出来ました。
これで、解決に近付くと思うと安心出来ました。
悪い口コミ
参考程度に読むと良いと思います。
不登校は、沢山の要因が積み重なって起こるので。
不登校初期にこちらを読んで、自分を責めてしまい本当に辛かったです。
最後までお読みいただきありがとうございました。