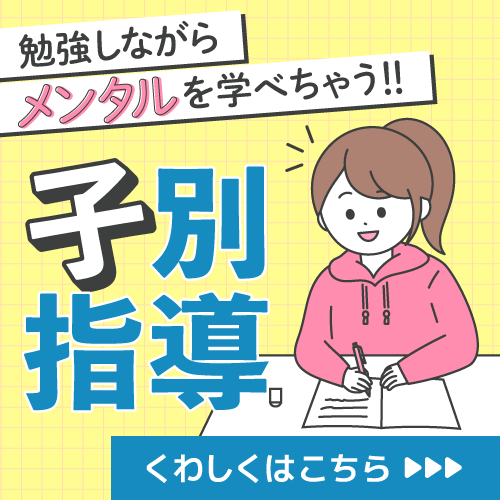カウンセラーである今野陽悦さんは、自身も不登校や引きこもりを経験した過去を持ち、その体験を基に、同じ悩みを抱える子の保護者の支援を行っています。
彼のカウンセリングは、子どもをどうにかしようとするのではなく、まず親自身が自己受容し、精神的に自立することに焦点を当てている点が特徴。
この記事が悩みを抜け出す一助になれば幸いです。
ポイント
-
自己受容の重視: 不登校解決の第一歩として、まず親が自分自身を受け入れることを提唱している。
-
「べき」からの解放: 社会的な規範や「〜すべき」という固定観念を手放すことが重要であるとしている。
-
柔軟な解決の定義: 「学校復帰」だけが解決ではなく、現実を受け入れて生活することも解決と捉えている。
-
当事者としての経験: 自身の不登校・引きこもり経験に基づき、共感と実践的なアドバイスを提供している。
カウンセラーの今野陽悦さんとは
今野陽悦さんは、ご自身の不登校や引きこもりの経験をもとに、同じ悩みを抱える本人やその家族をサポートしている日本のカウンセラー、著述家、起業家です。
中学生の頃から数年間にわたって不登校と引きこもりを経験し、親子関係の衝突や自己否定に苦しんだ過去があります。
その後、牧師でありカウンセラーである高木裕樹氏との出会いをきっかけに、自己受容の大切さを学び、カウンセラーの道を志しました。
現在は、不登校や引きこもりで悩む人たちへの支援活動や執筆活動を行っています。
基本情報と特徴
今野さんのカウンセリングや活動は、以下の5つの主な主張・提唱に基づいています。
-
自己受容の重要性: 親自身が自分をありのままに受け入れることで、子どもの現状も自然と受け入れられるようになり、精神的な自立を促せると説いています。
-
「べきの枠」からの解放: 「学校に行かなければならない」といった社会的な規範や固定観念から自由になることが、不登校や引きこもり解決に必要であると提唱しています。
-
「Being」を重視する生き方: 行動や結果よりも「自分はどうありたいか」というあり方を明確にすることの重要性を主張しています。
-
解決の定義の転換: 「学校に行く」「社会復帰する」といった結果だけでなく、「現実を受け入れ、上手に向き合いながら生活していく」ことも解決の一形態と捉える視点を提唱しています。
-
精神的な自立の大切さ: 親が子どもの問題に頼りすぎるのではなく、親自身が心の自立をすることが問題解決への大切なステップだと考えています。
これらの考え方は、ご自身の経験を基に構築された独自の理論と実践的なアドバイスが組み合わさったもので、多くの当事者とその家族を支援することに役立っています。
参考:「学校行きたくない」が増えてきた…不登校の初期、子どもの信頼を低下させる「やってはいけない」親の行動(講談社WITH)
メリット・デメリット
今野陽悦さんのカウンセリングやアプローチには、以下のようなメリットとデメリットが考えられます。
メリット
-
当事者目線の理解: ご自身も不登校・引きこもりを経験しているため、当事者の苦悩や葛藤を深く理解し、共感的なサポートを提供できます。
-
親子の関係性改善に焦点: 子どもを変えようとするのではなく、まず親が自己受容や精神的な自立を促すことに重点を置くため、根本的な親子関係の改善につながりやすいです。
-
柔軟な解決策: 「学校復帰」といった一つのゴールにこだわらず、「現実を受け入れて生活する」ことも解決と定義することで、一人ひとりの状況に合わせた柔軟な対応が可能です。
デメリット
-
即効性への期待とのギャップ: 親自身の心のあり方や考え方を変えることを重視するため、すぐに子どもの行動が変わることを期待する人にとっては、時間と労力がかかるアプローチに感じる可能性があります。
-
費用などは不明: メルマガなどに登録しないと講座やカウンセリング、個別支援の金額などはわかりません。
-
価値観の転換が必要: 「すべき」という思考からの解放や「Being」を重視するなど、従来の価値観を大きく転換する必要があるため、人によっては受け入れが難しいと感じるかもしれません。
向いている人と他との違い
今野さんのアプローチが特に向いているのは、以下のような人です。
-
長期的な視点で問題解決に取り組みたい人: 子どもの表面的な行動だけでなく、親子関係や家族全体のあり方を見つめ直したいと考える人には、根本的な変化を促す今野さんの考え方が響くでしょう。
-
親自身も変わりたいと願う人: 「自分が変わることで子どもも変わる」という考え方を前提としているため、子どもだけでなく、親自身も成長したいという意欲がある人に向いています。
-
従来の解決法に限界を感じている人: 「学校に戻すこと」や「社会復帰させること」だけが解決ではない、と考えるようになった人にとっては、今野さんの提唱する「解決の定義の転換」が新しい視点を与えてくれます。
他のカウンセリングとの大きな違いは、カウンセラー自身が当事者としての経験を持っている点です。
そのため、単なる理論やテクニックに留まらず、経験に基づいた説得力のあるアドバイスを得られることが期待できます。
また、親の自己受容や精神的な自立を最も重要なステップと位置づけている点も特徴的です。
多くのアプローチが子どもの問題行動に焦点を当てるのに対し、今野さんの方法はまず親の心の状態を整えることから始めるという点で、独自性を持っています。
口コミ、評判
(今野さんの本やブログ、音声などで勉強するうちに)
色んな私の中にあった執着を少しずつ手放していった感じです。
そうすることで、現実が少しずつ受け入れられるようになり気持ちが楽になっていきました。
今では息子に感謝です。
中3の子供が年末から不登校、行けない自分を価値のない人間だと自暴自棄になり自傷行為を繰り返しました。学校の先生もスクールカウンセラーも、心療内科もあてにならない中今野さんの書籍に出会いました。
自己受容の概念は何度も書籍や動画に触れ合うことで少しずつ掴めて来ました。
良い、悪いをジャッジしない、物事を全てありのままに受け入れることを心がけて子供に接したところ、死ぬことしか考えていなかった日々からいつのまにか新しい道を見つけ、親元離れ学校に通う決断に至りました。
また中学校をもう辞めたと言っていましたが、カッコ悪いから卒業まで通うと本人から言い出しました。
まだまだ気を引き締めてバイブルとして読み返したい本です。
細かなことに気を取られず、根本にある原因をありのまま受け止め、その事で自分を責めず、気づけた事を褒め自己受容を深めていけば自ずと好ましい方向へ行くというウソみたいな経験を本当にしている最中です。
初めまして。不登校カウンセラー?の今野陽悦さんってご存知の方、信頼出来る方かどうか教えて下さい。
高2の息子が不登校になり、妻が見つけたカウンセラーと名乗る方です。著書とかは出してるみたいなんですが、メールと電話でのカウンセリングで3ヶ月 35万円です。
信頼しても良い方なんでしょうか?ご存知の方がいたら教えて下さい。
一度ワークをしただけですが、それだけでも、親としての心がふっと軽くなり、それによって息子へ感じる感情が少し変わった気がしました。
特に自己受容という言葉がどうしても理解できずにいたのが、ワークを通して、少し分かった気がしました。
今野さんのメルマガ、音声で考え方、よかれと思っていたことが違うと気付かされました。
もっと早く、今野さんにそして本に出会いたかったです。今までの母として妻として○○であるべきの呪縛から私が解放されています。今まで、周りが○○であるべきベッキーさんだらけだったことで、必死についていこうとしていたのかなぁと思ったりします。
今までの考え方や発言に後悔もありますが、それも含め『あなたは悪くない』と癒してくれます。不登校だけてなく、なんだか自信なく生きづらい人も導いてくれる一冊だと思います。
まとめ:カウンセラーの今野陽悦さんとは
今野陽悦さんは、ご自身の不登校・引きこもり経験を強みとするカウンセラーです。
そのアプローチは、問題解決の鍵を「子どもの変化」ではなく、「親の自己受容と精神的な自立」に置いている点が最大の特徴と言えます。
従来の「学校に戻ること」を絶対的な目標とせず、一人ひとりの状況に合わせた柔軟な解決策を提示することで、多くの家族に希望を与えています。
しかし、このアプローチは親自身の価値観の転換と、長期的な取り組みを必要とします。
即効性を期待するよりも、根本的な親子関係の改善を目指す人、そして親自身も成長したいと願う人にとって、非常に有効な選択肢となるでしょう。
ご自身の経験に基づいた深い共感と、実践的なアドバイスは、不登校や引きこもりの問題で悩む人々にとって、新たな一歩を踏み出すきっかけになるかもしれません。
まとめポイント
-
自己受容の重視: 不登校解決の鍵は、まず親が自分自身を受け入れることにある。
-
「べき」からの解放: 社会的な規範や「〜すべき」という考えを手放すことで、親子関係が改善する。
-
柔軟な解決の定義: 学校復帰だけでなく、現実を受け入れて生活することも大切な解決策と捉える。
-
当事者としての経験: 自身の不登校・引きこもり経験が、深い共感と説得力のあるアドバイスにつながっている。
-
親子の関係性改善: 子どもを変えるより、親自身の心のあり方を変えることに焦点を当てている。
-
長期的な視点: 即効性を求めるのではなく、根本的な家族の変化を促すアプローチである。
-
「Being」を重視: 行動や結果よりも、「どうありたいか」というあり方を大切にする。
-
精神的な自立: 親が子どもに依存するのではなく、まず親が心の自立をすることが重要である。
-
デメリットの理解: 従来の価値観と異なるため、受け入れるのに時間と労力がかかる場合がある。
-
有効な対象: 従来の解決法に限界を感じ、親自身も成長したいと願う人に向いている。